
京大山岳部と剱沢大滝
2011.12.04
吉野 熙道

なぜ今更こんな古い記録や思い出を?
遺憾ながら、私は度重なる転職や転居、中国への移住、帰国などもあり、そのたびに保存していた山や研究関係の資料や書籍、実験データまでも処分してしまい、現在はごく一部のフィールド・ノート、写真、スライドとわずかな地図を手元に残すのみである。そのような状態でありながら、私が1969-1970年のブータン訪問、1973年のヤルン・カン(8,505m) 遠征の際に描いた稚拙なスケッチに続けて、剱沢大滝についても、AACK Homepageに投稿しておこうと思ったのは、たまたまAACKから「現ブータン国王から、京大のブータン訪問時の資料とくに写真があれば提供してほしい、との依頼があったので協力してもらいたい」という旨の連絡があり、手元に残っていた当時のスライドとスケッチを送ったのがきっかけであった。
しかしまとめておいたブータン関係のノートやメモもばらばらになっていたし、とくにスライドは、久しい以前から保存・管理が行き届かずにカビが生えたりこすれたりしていた。大変気になっていたが、しかし手入れをする余裕もないままに放置してきたのだ。それらの“残骸“とでもいってよい資料を見ながら、「こんなものでも発表しておけば何か役に立つかもしれない。しかもその当時は、他の人たちに散々お世話になり、自分でもそれなりに努力しながら実現できたことばかりなのだ」という思いが強くなった。
最近とくにNHK BSアーカイブズなどで、かつての記録が刷新されて公開されている。もちろんそれ自体はすばらしいことである。しかしそれらの多くは、ごく一部の成果の総まとめといってよい記録が、しかもマスコミ側の主観だけによって編集・発表されているのがほとんどである。このような風潮は看過できない。その陰で埋もれてしまう、いわば「前史」ともいうべき多くの記録も、せめてもう一度は現在のより改良された技術を用いて公表されるべきであろうと思う。
京都大学学士山岳会(The Academic Alpine Club of Kyoto、略称AACK)は、今西錦司・桑原武夫・西堀栄三郎・四手井綱彦氏たちの京都一中、三高から京大へと続いた登山・探検活動の延長線上に、木原均教授・郡場寛教授たちの支持と生物誌研究会(F.F.)、その他多くの方々の協力を得て創設された。隊員による学術調査を必ず伴う、その積極的で広範かつユニークな登山・探検活動は世界的に高く評価されてきた。
しかし残念ながら、AACKの積極的活動は、1973年のヤルン・カン初登頂とその直後の遭難、および1991年の梅里雪山 (6,740m) の全員遭難を最後として幕をおろした。それは、魅力的な未踏峰の消滅、ヒマラヤをも含めた登山のレジャー化、若者たちの行動目標の拡大・拡散化、むしろ消失など、さまざまな社会事象・環境変化などに伴い予想されていた結果であった。もちろん会員の間ではずいぶん前から「AACKはどこに行くのか?」という議論はなされていたが、はっきり言ってそれらは結局「悪あがき」にすぎず、少なくとも地理的なフロンティアー活動は時代の流れの中に埋没せざるを得なかった。
AACKの蔵書や公表された記録は「登山探検文献センター」に収められ、そのうちの電子化・整理されたもののみは京大図書館が受け入れてくれたということは聞いていた。しかし問題なのは、その間に多くの原資料や根気よく続けられていた活動の記録などはいったいどうなったのかがよくわからないことである。AACK事務局が保存していて、責任ある立場の人は、経過と現状を把握しているだろうとは思うが、私などのようにここ数十年間も京都や登山から離れていて事情に疎い者には、どうなんだろう?とわからないことだらけである。つい先日から酒井敏明(オシメ)さんたちの発案により、「AACKアーカイブズ」を整理しようとの活動が始まったところを見ると、漠然とした不安というか、落ち着きの悪さを感じていた者は私だけではなかったのだなと思った。AACKばかりでなく、かつてはその母体の一部であった山岳部の活動も永らく低迷していて、部員数も大幅に減少していたとのことだ。水曜会の議事録やルーム日誌、皆で集めたヒマラヤや南極の資料、私が吉井良三先生にお願いして山岳部に寄贈していただいた三高山岳部の「青雑誌」などはどうなったのだろうかと思う。
71歳ともなると、自分の資料や記憶もまったくいい加減なものになってしまった。しかし剱沢大滝での京大山岳部の活動を知る人が少なくなってしまった今、いかにわずかではあっても手持ちの資料と写真は公表すべきであると思い、雑なまとめで、恐縮の限りではあるが、ホームページに投稿することにした。
剱沢大滝に至った京大山岳部のバック・グラウンド
京大山岳部は毎年夏には剱沢の真砂沢出合(時には穂高涸沢)にテントを張り、岩登りを中心とした合宿を行なってきた。1960-1970年代は部員数が40名ないし60名以上と多かったために、7月下旬から8月上旬にかけて、新人に対する、登山の基礎・雪渓・岩登りの訓練とともに上級生の技術向上を目的とした合宿を、前期・後期に分けて行なうのが常であった。これ以外の通常の山行は4ないし6、7人の小人数によるパーテイーを多数送り出すのが普通で、夏山などには多い時には合計30パーテイー以上もの山行があった。合宿はこれ以外には、1回生の11月の富士山でのアイゼン訓練と12月から1月にかけての妙高高原・笹ヶ峰ヒュッテでのスキー合宿だけであった。他のほとんどの大学山学部は、ふつう全員による合宿中心の山行をしていた。しかも彼らの多くは、いわゆる体育会系運動部に見られる、旧軍隊のような「シゴキ」による新人訓練と傲慢無礼・前近代的な上級生への絶対服従を当たり前のこととしていた。まだ体力も技術も伴わない1年生が一番重い荷物を担がされ、上級生はうしろから軽い荷物だけを持って行進する。また極端な例であるかもしれないが、1日の行動が終わった時に、ふんぞり返った上級生の靴ひもを1年生がほどく、などという信じられない光景もよく見られたのだ。とうてい大学生とはいえない低能ぶりとしか言いようがない。
この点で、京大山岳部は大きく異なっていた。それは何よりも、「パイオニアー・ワーク」という目標と「オールラウンドにしてコンプリートな山行」に対するこだわりに表れていた。このこだわりは単なる標語以上のものとなって、メンバーの日常生活にもしみついていたと言ってよい。外部の人は、京大が探検大学と呼ばれるような戦前からの実績を持ち、また湯川博士のノーベル賞に結実した先進性、官僚の母体となっている東大に対して滝川事件などに示された在野性とアカデミックな精神を有するだいがくであることを、漠然とではあっても知っている。しかし「山岳部」といえば、「シゴキ」とすぐ連想される、体力第一・序列絶対のゆがんだ精神主義が支配的であるのは当たり前と考えられていて、たとえ京大といえどもその点では同類と思われていた。現に私なども浪人中に慶応大学の山岳部員であった高校の先輩に、京大に行って山岳部に入りたいという希望を話した時、「京大かー、さぞきついだろうな」と言われた。彼は心配そうに私の細い体を見やったものだ。だから入学式直後の新入生に対する部の説明会で3回生の新人係が「京大ではシゴキはやりません。あくまでも自主性を尊重します」と言ったって、全然信用しなかったのだ。
しかし北山への新人歓迎山行、5月山、夏山と過ぎ、またその間に山行計画検討会や部の運営を中心とする、水曜会での全員一致を原則とする徹底的な合議制の中で、未熟な1回生ではあっても自らも思うところを述べる経験を重ねた。そしてまた山岳部のルームでばかりでなく、ヒマラヤやカラコルムの経験者さえ含む先輩や上級生、同回生の下宿で、さまざまな知識を吸収しつつ、談論風発する中で論理の鍛錬さえ学んだ。それは山行中の食後の一時などでも行われた。一種の理想的なセミナーと言えるものだった。少しあとになるが、雪山での悪天候による沈殿日(私たちは「チン」と呼んでいた)には、下級生から始めて皆が、自分の専門分野における勉学や卒論の状況や興味を抱く対象や趣味の世界など、なんでもよいからレクチャーを行うのが常であった。必要最低限なこと以外には何もすることがなくメシさえ半分に減らされるチンの日には、シュラーフをひっかぶって口だけを動かすこんな作業は絶好の時間つぶしなのだった。
このような生活を経験すれば、わずかの間によその多くの大学山学部や社会人山岳会とは全く違う思想、登山に対する考え方を身につけていくのは当たり前であった。
なぜこのようなちがいが生じたのだろうか?一つには、京都という長く困難が続いた歴史を持つ町の重み、その中でしぶとく生き抜いてきた町衆の雰囲気がそこここに感ぜられる町の伝統の自信があるだろう。京都は、新興勢力の大勢には染まらず、しかも新技術や新知識に対して批判的な目を向けつつ冷徹な判断を下して、いつのまにか自分のうちに取り込んで新たに展開してしまう、というふてぶてしさを持つ町と人なのだと思う。
そこに集ってきた京大の学生全般に言えるのかもしれないが、山岳部には京都の出身者は1割もいないし、また山などの経験は無いといってよい者ばかりであったが、京都”的“な物の見方、山岳部の目的や方針に抵抗感をおぼえずに入れる素質を持つ人間が多かったように思う。「生意気な」奴が多かったと言えるかもしれない。悪く言えば我が強い、良くいえば個性が強い、である。そんな人間が、自主性を持って自由に自分の意思を表明できる環境の中で良い方向に向かえば、急速に成長できる可能性があるのだった。
京大山岳部では、毎年10月に部の執行部が交代した。リーダー1名、サブリーダー2名、新人係1名、会計係を兼ねるマネージャー1名、ヒュッテ係1名が3回生の合議で選ばれ、それを水曜会が承認する形を取っていた。各山行についてはパーティー・リーダーとサブリーダー1名ずつが推薦され、水曜会が承認した。
どの回生であろうと自分で山行計画を立案することができる。それに賛同したメンバーが数人集まれば自然にパーティー・リーダーが決まるのが普通だったが、下級生がリーダーをリクルートすることも多かった。立案から水曜会での検討に耐えての承認、山行の実施、終了後の山行報告会、山岳部報告の原稿執筆と進むうちに、お互いの人柄、長所、欠点などが共有される。それらがかみあわずにギクシャクすることがあるのは当然だが、山岳部ではどういうわけかそれが致命的になることはまず皆無であった。それは合議制を原則としながらも合理的で強いリーダーシップと自主的なフォロアーシップがうまく機能していたからだと思われる。そのベースにあるのは、「個性を認めその人格を尊重する」というごく当たり前のことである。個性の強い人間の集まりであるだけに、好悪の感情を越えてとにかくまず、他人の個性は自分の個性と同じ価値を持つことを認めねばならない。だいたいそうでなければ、自分の個性さえも否定することになるのだから。だから自分の意見はあくまで主張するが、リーダーがひとたび決定したことにはフォロワーとして全力を尽くして協力する。一方リーダーもけっしてゴリ押しはしない。なぜそうなるかといえば、いくらフォロワーとして万全であっても、彼らのすべてが優れたリーダーになれるとは限らないからだ。優れたリーダーになれるのは、やはりごく一部の人間であるからだ。だれがリーダーにふさわしいかは、ある水準以上の知能を持った人間が冷静に判断すれば、つきあい始めてすぐにわかってくるのだ。
このような背景の中で積み重ねられてきた山行の多くは、その都度組み合わせの異なる様々な個性が一つの目的に向かって議論を尽くして練り上げた計画が全員参加の水曜会の検討を経て実行された。登りつくされた観のある国内の山であっても、どこか一工夫こらした計画が追求された。1950、1960年代には、日高、知床、東北はもとより、北アルプスにおいても黒部川、剱岳をめぐる当時まだ完全遡行の成されていないいくつもの谷があった。それらを目指す人々もいたが、谷川岳や穂高での初登攀ルートを狙うほうが登山関係の雑誌などで華やかな扱いを受けることが多かった。その中で京大は黒部川を中心とした未開拓の沢登りに集中した山行を行って成果を挙げてきた。当時一部の人には名前だけが知られていて「幻の大滝」などと言われていた、剱沢大滝を登ろうという機運が高まってきたのは、当然と言えば当然の成り行きなのであった。
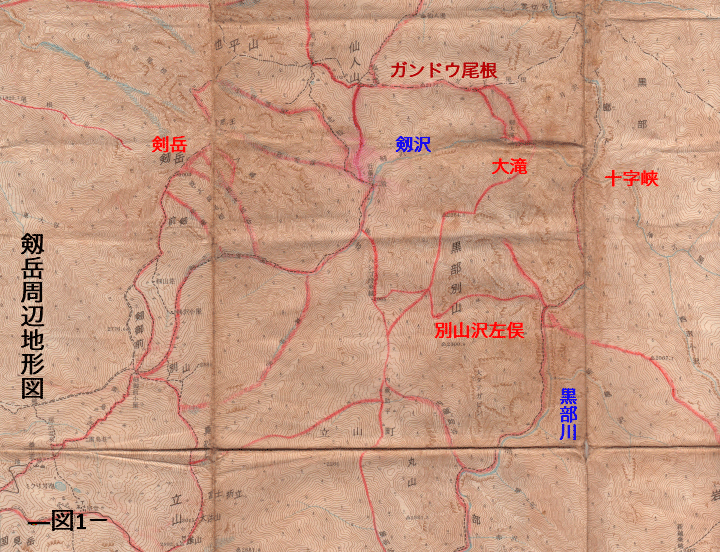
剱沢大滝への山行概要
開拓期・冠氏他 (1)
黒部といえばなんといってもまず冠松次郎氏の名前を挙げねばなるまい。氏は名案内人として知られた宇治長次郎氏をガイドとして黒部渓谷周辺の山々をくまなく探索して、多くの著作を残しているが、その「黒部渓谷」(1) には、6月の「剣岳・大滝・剱沢」と題した写真があり、「中央の滝は大滝200米、下の流れは剣沢」と解説され、中央にはっきりと大滝最下段が写っている。これは黒部対岸の棒小屋沢側から撮ったものにちがいない。大滝を写した最初の写真であるだろう。本文中には、大正14年8月から9月にかけて上廊下を遡行した記録がある。また大正15年6月7日から室堂、内蔵ノ助平を経て11日黒部別山に至り、剱沢右岸、大滝のはるか上部へ少し下降、12日も十字峡側に下降を試みているが、それらのいずれにも、大滝最下段が見えたという、上記の写真に関する記述はない。
さらに冠氏は1927年8月に別宮氏、岩永氏、宇治氏とともに、十字峡から大滝最下段に達した。「回想の剱沢」にその高さを約50mと記した。また、1929年6月初旬には再び岩永氏、宇治氏と剱沢を下降し、雪渓の下をなんなく大滝の真上まで達した(安岡良祐 (6) による)。私は現在この両記録の出典については知らない。
また宮木靖雅 (4) によると、「冠氏が十字峡上方の東信歩道よりとった写真(修道出版:黒部)に上段と下段の滝が写っているがこの二つの滝は同一方向に走っておりしかもその間にはかなりの高度差があり当然一つあるいは二つの滝のあることが予想される。」とのことである。これは1961年12月刊行の報告だから、私はこれを見せてもらったはずだが、記憶がない。宮木はすでに故人であるのでここでは言及できない。
開拓期・塚本氏他1931年11月 (2)
次の大滝に関する記述は、塚本繁松:「剣の大瀑行」(2)である。それによると、1927年夏の新聞に冠氏の大滝発見、「高さ数百メートル」との新聞記事が出た。また1931年夏から秋に日本電力が大滝の測量を行い、3段、上からそれぞれ約4、50尺、150-160尺、120-130尺とのうわさであった、とのうわさだったという。
測量に従事した人夫の竹山幸右衛門氏を案内人として、1931年11月8日鐘釣温泉を出発し、十字峡の日電の小屋で泊まった。翌11月09日最下段の滝に至った。左岸岸壁に2本の鉄線製の縄梯子が残されていたが、1本は落石で痛んでいたので切り落とし、もう1本とロープをつたって左手上流側に針金が張ってあり、「それを伝って岸壁をトラバースして下段の滝の方に出たが河岸へ下ることはできなかった。流れの上五,六十尺のところに少しばかり灌木の生えた小さな平があり、そこがこの道の行き止まりであるとのことである。下段の滝口から、四、五十間で中段の滝つぼである。けれども滝が見えない。(中略)滝を見るためには今四,五十尺岩登りをせねばならぬとのことでロープをたよって上った。(中略)中段の滝の全容をながめることができた。しかしこの滝は思ったほど美しい滝ではなかった。高さは下段の滝より高く百五十尺をこえるとのことだが私の目にはかえって低く感ぜられた。そして下段の滝のように一気にたぎり落ちているのではなくて岩床に相当の傾斜があり、それをすべり落ちてくる感じである。そして下の方に岩の突起があってそれに水がぶつかって滝の一部がはねかえっている。」さらにわずか上段の滝までは行けなかった。「中段の滝上四,五十間上流の岸壁に一本の赤旗がたっている。私の上がっている五葉松の枝にも一枚の赤旗がつるしてある。」測量時には仙人谷を回って剣沢の二股に下り、下行して上段の滝に出て赤旗を立てたところでこの木の枝の赤旗と連絡して測量を曲がりなりにも終わったのだそうで、この付近の測量は全く命がけであったとのことである。私は木の上へ写真機をつり上げて数枚の写真を撮ったが何しろピントグラスものぞけず、胸にあてることもできなかったので、後でみるとどれもこれもわずかのことで滝つぼが入っていなかったのは残念だった。」その後十字峡から宇奈月へ帰った。竹山の話によれば、上段の滝は中下段に比べてずっと小さく、三十尺以上、五十尺以下だそうで、「三つ合せて百メートルをこえないことが確かとなったわけだが、上段の滝の落口から下段の滝の滝つぼまでの落差は二百メートルといってもよいかも知れぬ。」
塚本氏はこのように詳細に記述していた。運よく竹山という現場に詳しいガイドがいたという幸運もあったとはいえ、このような早い時期によくなしとげたものである。それにもまして、日電の測量隊はよくもまあ貴重な仕事をやりとげていたものだ。当時の山働きをしていた人々の体力・気力・技術のすばらしさには感嘆するほかないが、彼らを率いていたリーダーがよほど優秀な人だったのだろうと推測される。このあと、我々京大山岳部と他のパーテイーが大滝に挑戦したわけだが、うかつにもこの記録を知らなかったので、結果論とはいえ、ずいぶんとむだな労力や推測に時間を費やしたことになる。
残念なのは、塚本氏が撮影した写真や概念図を記載していないことである。他の機会に発表されたのかもしれないが、寡聞ながら知らない。
京大 1960年4-5月 (3)
その後京大山岳部は剣岳、黒部川周辺の山や谷に多くの山行を重ねていた。たとえば1960年3月の鹿島槍岳―十字峡横断―剣岳、猫又谷、柳又谷、北又谷、小黒部谷などの遡行である。とくに十字峡横断の際には大滝を垣間見たという。そして大滝に直接入って行ったのは1960年からであった。
宮木靖雅 (3) による1960年4月28日から5月7日までの山行概要は以下の通りである。
(ルートなどに関しては、図 3を参照。)上市から白萩川、剣大窓、仙人山から、ガンドウ尾根を東へたどり、大滝のすぐ下流に至る雪渓(これを「滝見沢」と呼んだ)を下り、5月3日に大滝最下段、十字峡往復の後、黒部別山を経て5月7日剱沢二股から大滝まで雪渓を下った。宮木は「川巾が急にせばまり傾斜がきつくなった所で雪渓が切れている。(中略)雪渓の切れた部分はナメ滝になっており、(中略)(冠氏はこの大滝を3段あるとされているがこのナメ滝がその最上段のものであるかどうかははっきりしない。しかしこの地点から最下段の滝までの間にかなりの高度差があるのでこの間にもう一つの滝のあることも十分考えられる。」と記している。この後大窓より下山した。なおこの時最下段の滝の高さを「約50m程」と見当をつけた。
京大1961年7月 (4) (5)
続いて1961年7月11日から7月20日にかけて、ガンドウ尾根から南に大滝に向かって下る大滝尾根を登攀した。宮木靖雅 (4) (5) の報告概要を以下に示す。
5月に下りた雪渓に入ってから、大滝尾根の頭(ガンドウ尾根上2,173.1mの三角点から東に750m、標高2,000mの独標)から尾根上部の偵察と荷物のデポを行った後、7月18日より登攀開始。II峰(図 4参照)の下30mのテラスから最下段の滝落口とその上のナメ滝を見た。II峰からはこのナメ滝の「更にその上の釜が見える。滝自体は右手に曲がっており岸壁のかげになっている。これで下から三つ目まで確認できたわけである。」IV峰、V峰、VI峰の岩稜の岩登りを楽しんだ後ヤブをこいで大滝尾根の頭に着いた。
京大1962年7月 (6) (7) (8) *
次に1962年7月14日から7月25日にかけての、安岡良祐 (6) による大滝最下段の登攀記録がある。本山行は読売新聞社の強い要請により、同社の資金援助も受け、カメラマン1名を同行して、大滝の完登も目指すという野心的な山行であった。当時はそろそろ、岩に鏨で穴をうがって打ち込む「埋込ボルト」やアブミを使って裂け目のない岸壁を加工して登る、いわゆる「人口登攀」を行う山岳会も出現してきていたが、我々はそのようなやり方は邪道であり、あくまで最小限の道具のみで自然に手を加えることなく登山すべきだと考えていた。はっきり言って、そのようなやり方を「石屋さん」と馬鹿にしていたのだ。しかし大滝内部の圧倒的な岸壁に対しては通常のハーケンのみによる登り方では通用しない可能性が高いので、あえて使用しなければならないことも考えて、八瀬静原の金毘羅山ロック・ガーデンでの試用も行なったが、結局使用はしなかった。
読売新聞社は事前に全国紙上の社告で本山行の予告し、ある程度の資金援助もしてくれるなど、本計画には大変熱心であった。ただこの時に読売側は、剱沢大滝に対し、「幻の大滝」なる表現を用いた。これはいかにもジャーナリスティックで陳腐な表現で、私としては気に食わなかった。
実はこのころ山岳部では、以前から2回生が中心となって進めてきたヒマラヤ遠征計画がやっと実現の運びとなった。インド政府からパンジャブ・ヒマラヤの未踏峰インドラサン(6,221m) とデオ・テイバ(6,002m)の登山許可も得て、募金や登攀計画などの具体的準備が始まっていたため、通常の山行計画もやや縮小・抑制的なものにならざるを得なかったが、この大滝山行だけはそれまでの蓄積もあり、山岳部の全員合意による最高の意思決定機関である「水曜会」の承認を得られた。これに関しては実は現実的なせせこましい事情もあったのだ。今でははっきり覚えていないのだが、当時部費が毎月数百円単位、生協食堂での素うどんが15円かそこらであったと思う。このような財政状況では、ハーケン1本、ザイル1本買うのでさえ大変な出費であった。ましてテントなど買えたものではなく、ほとんどの主要テントはAACKからのお下がり品で、大型のメステントなどは知床、チョゴリザで使用されたもので、凍りついた時に運ぶのは大変重くかさばって非常につらい代物だった。高度成長経済の恩恵はいまだ貧乏学生にまで及んではいなかった時代で、山岳部の財政は常にピンチだった。このような状況下で、読売新聞社が後援の名目である程度の資金提供をしてくれるという話は、部にとっては願ってもないことであった。
滝見沢(図 2、3、4、5)を下って、7月18日に剱沢左岸側にテントを張って大滝に対面した(図 7、8)。前年は雪渓上を簡単に最下段下の右岸に渡ってテントを張れたのに、この年には雪渓はなかったので右岸には渡れなかった。左岸側は垂直の岸壁で滝壺には到達できない。下流側も急流と小滝があって渡れない。大滝尾根下部を登って左側のルンゼを下りるのも無理とわかり、橋をかけるしか手がないこととなった(図 10)。19日いっぱいかかって岩を登り、やっと架橋用の短い2本の松の丸太を切り落とした。しかし翌1日かけても、水量の多い急流と丸太の長さが足りないために架橋できなかった。21日に流れの中央にある岩に1本の丸太をわたし、そこから吉野が流れに飛び込んで、少し上流側の岩にはい上がり、そこから丸太をかけて安原が右岸に上がりザイルを張った。これで左岸から右岸までチロリアン・ブリッジで渡れることになった。また滝壺の下を吉野と安岡が徒渉してフィックス・ザイルも張れた(図 9)。作業の困難さと水しぶき、雨のために胴震いがするほどの寒さで、途中何度も休んでは体を温めなければならず、時間ばかりかかってしまった。さらに滝の高さを三角測量できたが、約38mで思いの他の低さであった。
23日晴天となり、吉野と安岡がいよいよ左岸の壁にとりついた。岩や草つきが交錯している壁なので、吉野は地下足袋、安岡は登山靴で、10時から登りだした。登攀ルートは図 12 と13 を参照してもらいたい。最初のピッチの短い凹角に少々手こずった他はズルズルの岩の草付きがいやらしいくらいで、難しい登攀ではなかった。驚いたのは、最後のピッチ(図中FとGの間)で15mほどの黒さびの針金とそれを止めているボルトを見つけたことだった。30年前に日電の測量隊が取り付けたものであることはまちがいない。大変しっかりしていて、まだ十分頼りになるものだった。そこから30m左上して小さな檜に達した時はすでに16時前になっていた。さらに40mいっぱいザイルをのばして、巾10m、長さ30mほどの大テラス(図中のG)に吉野が着いた。ここには古いたき火のあとがあったので、ここを「日電テラス」と名づけた(しかし、このあとまもなく鵬翔山岳会が「たき火のテラス」と称して私たちより先に発表してしまった。)吉野は容易にテラスの末端に達し、最下段の滝落口からの上流側を見た。
「テラスの末端(上流側)に着く。見えた!30mはあると思われるいくらかナメ状の美しい滝と、それより高く上がる噴煙が目に飛び込んでくる。30数年ぶりに近々と人間の目にふれる滝である。周囲はほとんど垂直でつるつるの壁が数百m、両側から押しあうように狭まり、すでに夕方であるので陽射しも入りこまない。滝を見ているというものでない。ただ滝があるのだ。自分は全く別の世界をのぞき込んでいるような気がして茫然としていた。心配したのだろう、安岡がザイルを引張ったのでやっと我に返り、写真をとりまくった。日電人夫も塚本氏もここからの写真を撮れなかった筈だ、と思うと少し興奮してきた。滝の下に滝壺が見えるが、どうもナメ状の滝のものではないらしい。必死にそれを確かめようとしたが岩にかくれてとうとう見ることができなかった。又その滝壺からは水流が一気につっ走っていて、最下段の滝の上の滝まで続いているらしい。」(写真 16、17、18)。
結局橋かけに4日もかかってしまったために、肝心の大滝登攀にはこの日1日しか使えなかったのは、いかにも残念であった。せっかくなけなしの金を出してボルトまで買って(この頃は通常のハーケンの何倍もの値段だった)練習までしたのに、と悔しかったがしかたない。
(なお、図中の「草付きのテラス」としたものは鵬翔山岳会が「緑の台地」と称したものである。)
25日仙人小屋に帰り下山した。高岡市の読売新聞本社で座談会形式で報告をして、これは全国に配信された (7)。しかしその時、我々の入山の時朝日新聞社が、当時日本に1機しかなかったジェット・ヘリコプターをチャーターして、2段の滝が写っている大滝の写真を写真ニュースとしてスクープしていたことを知った(8)*。いくら競争の激しいマスコミ業界だとしても、そのアンフェアーな取材には腹が立った。それまでは朝日新聞と言えば日本の良識を代表する、と思っていたのだが、これですっかり幻滅した。大滝のすばらしさを汚されたようにさえ思った。
この山行では、まったく新しい発見ができたとはいえず、先人の成果をなぞる結果になったわけだ。少し残念ではあったが、これでさらに大滝の全容解明と完全遡行の可能性は見えてきた、と先に希望をつないで帰京した。
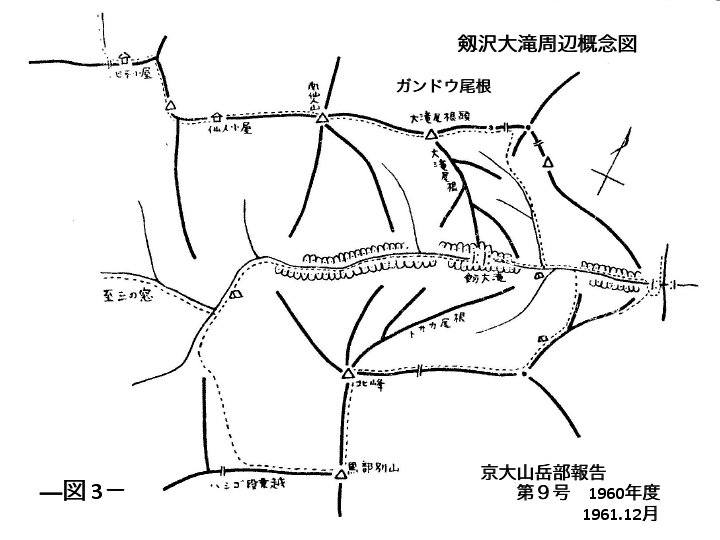
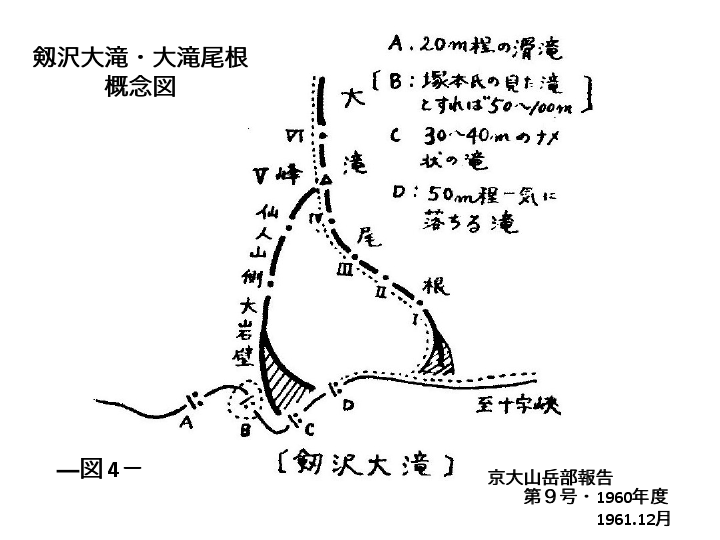



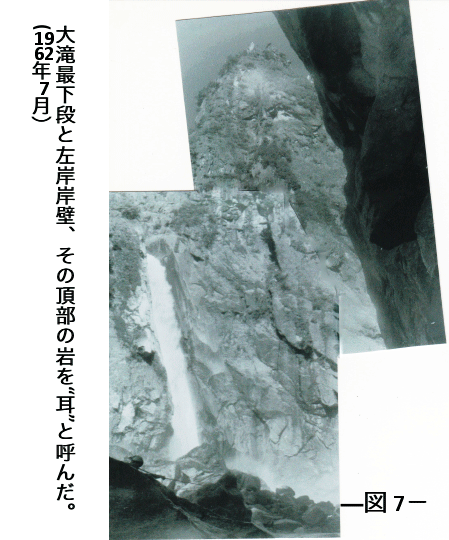


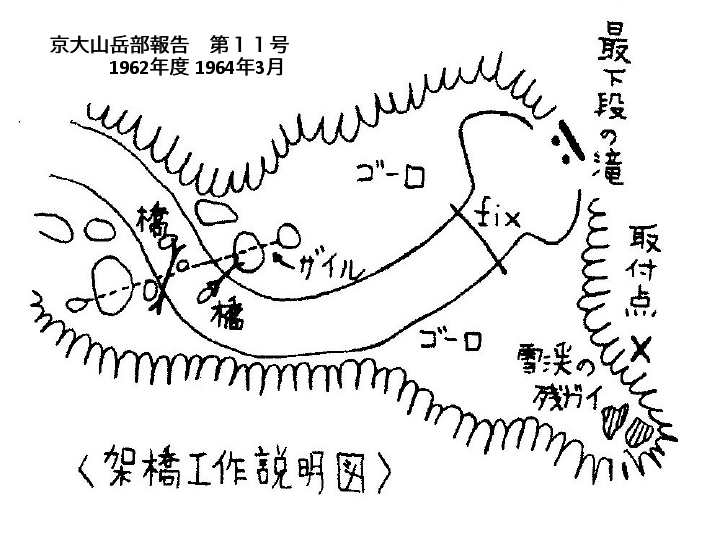


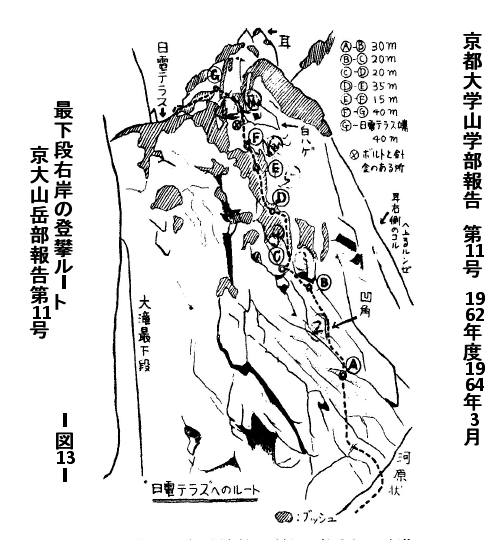
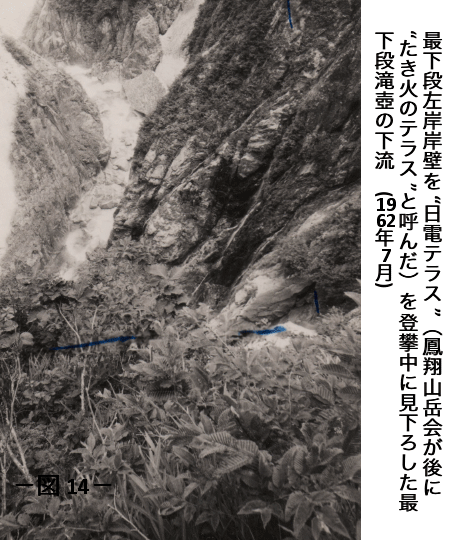

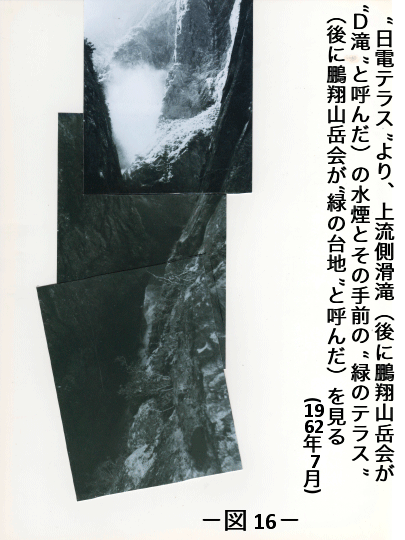
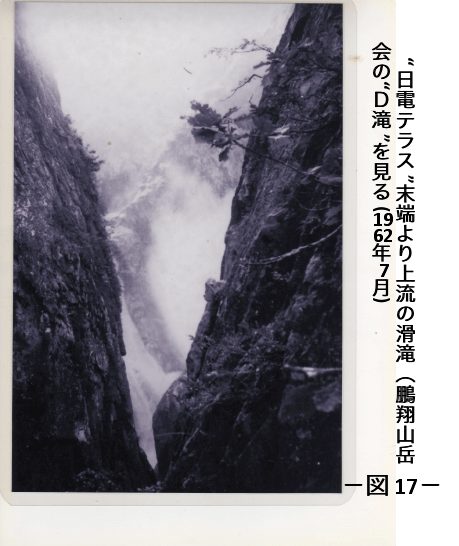
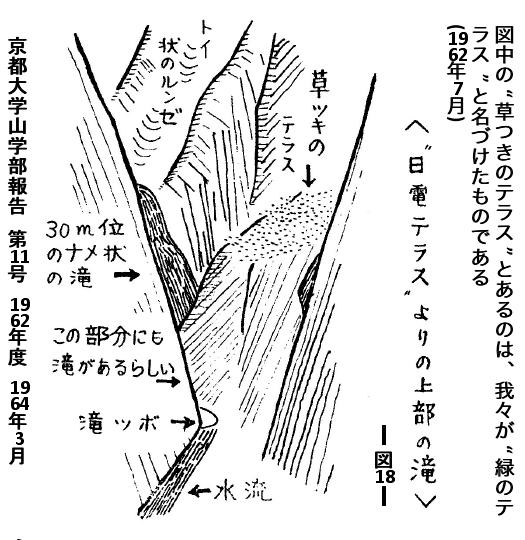
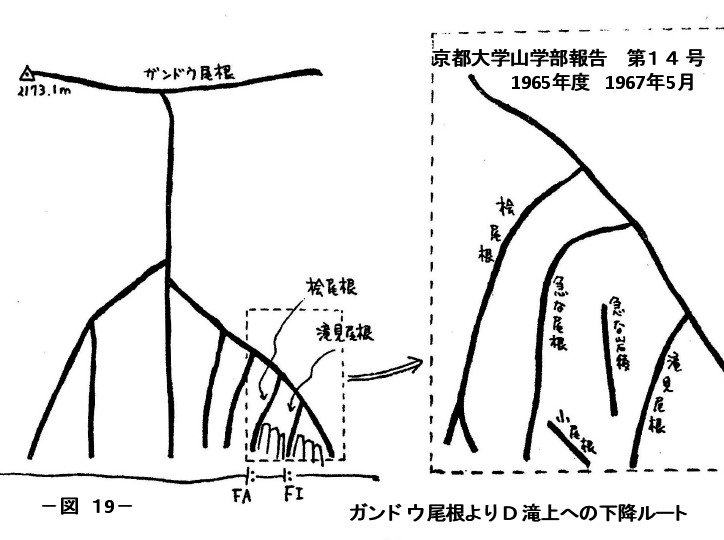
ここでいったん大滝から離れて、その後の山岳部の諸事情について述べることとする。
インドラサン初登頂1962年10月 (9)、北穂高滝谷遭難、西イリアン遠征 (10)
10月山のあと慣例により山岳部のリーダーは3回生に交代した。私はリーダーになった。
以前から2回生だった私たちを中心に「ヒマラヤ研究会」が遠征実現を目指して地道な勉強会を開いていたが、山岳部主体のヒマラヤ遠征を実現しようという機運が高まってきた。
学生隊員の構成は4回生1人、3回生2人、2回生1人と決まって、各回生がそれぞれのやり方で選考を行った。
山岳部長の多田政忠・理学部教授を初め多くのAACKの人たちも、大学山学部現役学生を中心とする初の遠征隊ということで積極的に支援してくださり、小野寺幸之進・農学部教授を隊長、ノシャック初登頂者の酒井敏明(オシメ)さんを副隊長も決定した。酒井さんはまだ地理学博士課程の院生であった。隊員は、大森義次(ゲジ)、田中二郎(ジロウ)、宮木靖雅(トク)、岩瀬の4人に決まった。山はインド、パンジャブ・ヒマラヤのピル・パンジャール山群中の未踏峰、インドラサン(6,221m)に決まった。
遠征隊は10月13日にインドラサンの初登頂とデオ・ティバの登頂を果たして、11月29日以後順次帰国した (9)。インドラサンは急峻な岸壁を擁し、困難な登山であったが、現役山岳部員の力はヒマラヤでも立派に通用することが証明された。
しかしその喜びのさ中、11月山行で穂高縦走中のパーテイーの2回生の加納洋が北穂高岳滝谷に滑落し行方不明となった。同行者は谷を下降し捜索を試みたが、まだ浅く不安定な積雪・着氷と悪天候のため、断念して下山した。在京の部員とAACK会員、山行から帰ったばかりの部員が順次救援に向かった。結局遺体は発見できないまま年を越した。その後北穂の小屋に切れ目なしに捜索隊を入れ、また滝谷下流からも監視を怠らず、遺体や遺品の流失防止のために下流にしっかりした柵も設けた。すべての山行は中止を原則とし、笹ヶ峰ヒュッテでの合宿のみとした。
ついに6月、遺体が発見され、上高地で荼毘に付された。加納は戦後の山岳部における3人目の犠牲者となった。ヒマラヤ遠征の成功によって過大な自信をいだいて、力量以上の山行をしたのではないか?など、深刻な反省の気分が部にみなぎり、活動は低迷した。
ところがそんな時に突然、ニューギニア遠征、それも探検部との合同遠征という話が持ち上がった。1963年5月、オランダ領だった西イリアン(イリアン・ジャヤ:西部ニューギニア。インドネシア領となったが、その後紆余曲折を経て2000年6月「パプア」として独立)のインドネシア帰属を記念するために、親日家だった当時のスカルノ大統領が、両国合同の登山隊をニューギニア最高峰である「カールステンツ・トップ」(5,039m、後「スカルノ・ピーク」、現在は「ジャヤ山」)に送るという提案をしてきたのだ。この山は未踏峰ではないが、頂上付近には氷河を抱くという。この地の全土はほとんどが深い熱帯雨林におおわれている、現地の住民は多くの部族に分かれて言語も通じないほど、互いに争っては首狩りをする、いまだにほとんど鉄器を知らず石器時代の生活をしている、等々さまざまな断片的情報が飛び込んできた。
AACK、探検部と話し合い、部内でカンカンガクガクの討論が交わされた。なにしろ遭難がやっと片付いたばかりだ。たしかにめったに出会えない面白い遠征なのだが、山の対象としては未踏峰ではないし、政治的に利用されるだけだ、という意見が多かった。しかし、4回生の水瀬(サウド)と3回生の松田(ランプ)は「こんな時だからこそ行きたい」と、参加を強く希望した。吉野は内心このような遠征もパイオニアー・ワークであろうと思っていたので、最終的には参加の方向を支持した。結局AACKの安江安宣・農学部教授を隊長とし、田附重夫(ガイガー)・東京工業大学助教授、探検部の2名と山岳部の2名の隊員、さらに朝日新聞社の後援が決まって、同社から探検部の創設者である本多勝一氏、写真部の藤木高嶺氏という隊が成立した。同隊はインドネシア陸軍の精鋭部隊とともに無事登頂を果たして、多くの珍しい経験と収集品、情報を得て帰国した。
本遠征隊に関しては、本多勝一 (10) も参照されたい。
ガネッシュ・ピーク初登頂1964年7月 - 1965年2月 (11)
ここでまた山岳部と私の話に戻る。1963年、私は4回生になった。大学院の試験にも通った。卒論の実験も始めた。しかし私は一種のうつ状態で、毎日浴びるように酒ばかり飲んでいた。とにかくも私はヒマラヤに行きたいから京大山岳部に入ったのだ。インドラサン遠征に際しては、2回生同士で1名の隊員候補を決める話し合いをしたのだが、自分はまだ十分な技術・体力・知識が身についていないから今回は立候補しない、しかしもう少し鍛えたら必ずヒマラヤに行く、と決めていた。それなのに遭難があったためにその後始末だけに終わって卒業になるのか!と思うと、むしゃくしゃするのだった。卒業後にAACKの隊員になって行けばいいのだ、という考えもあるし、その方が確かにまともなのだが、その頃の私は自分の山の実力に大変な自信をもっていた。今が一番脂がのりきっている、今ならどんな山でも登れるのに、とがまんができなかった。1年上級の宮木(トク)も卒業前のヒマラヤ行を考えていたので、2人で行けるだけ行こうと決めて、とりあえずネパールからの招待状を取り付けるべく行動を開始した。当時はまだ自由に海外に行くことなどできなかった。相応な理由と旅費・滞在費を保証してもらえなければパスポートや外貨(為替レートは1ドル360円の時代だった)の割り当てをもらえなかったのだ。
ほうぼうを当たってみたが、なんとかつてを頼ってわずかな食事代のみでカルカッタまで運んでくれる貨物船も探した。少なくとも半年、できれば1年間ヒマラヤ乞食旅行を実現するのだ。パスポートと200ドルの外貨も買えた。
ところがこの時に至って、部内の空気が変わってきた。最初は「遭難時のリーダーがヒマラヤ?そんなの許されるんか?」という雰囲気であったが、「コッペ(吉野)だけではなく、部の活動としてヒマラヤ遠征をしてもいいんじゃないか」との意見が徐々に大勢を占めてきたのだ。しかしやはり多くの部員の心の中には(遭難以後の抑圧されたエネルギーをなんとか発散させたい、しかしそんなこと言えんしなあ)といった葛藤がうずまいていたのだろう。吉野がそれに火をつけてしまったのだ。大分もめたのだが、結局水曜会は「今度は本格的にネパール・ヒマラヤをねらう、それも7,000m級を」ということで一致した。酒井敏明(オシメ)さんがインドラサン以来の縁もあって熱心に現役を応援してくれ、山岳部長になっていた小野寺教授の説得はもちろん、隊長探しにも知恵を絞っていろいろな人に交渉してくれた。京大防災研究所助教授の樋口明生(ジャン)さんの中書島の研究室に頼みに行くと、即刻「ええ話やなあ」とニヤリ。うれしかった。樋口さんはすぐ研究所の了承をとってくれて、正式に隊長に決まった。副隊長はAACKの若手No.1でサルトロ・カンリ隊員でもあった上尾庄一郎さんが引き受けてくれた。隊員は前回同様各回生内での立候補により水曜会で決定された。5回生の吉野、4回生の木村雅昭と島田喜代男、3回生の上田豊である。
問題は対象の山であるが、初めはダウラギリIV峰(7,661m)が有力で、カンジロバ・ヒマール主峰(7,043m)とされていた)と競り合ったが、結局アンナプルナ南峰(別名ガネッシュ・ピーク、7,256m)を申請した。この山は登攀ルートに関する情報は一切なかった。もちろん試登がなされたことはない。とんでもない掘り出し物だったのだ。登山許可はすぐに下りた。私たちの気持ちは一気に盛り上がって全ての準備も整い、ガネッシュ遠征が始まった。この隊は首尾よく10月13日に中央峰、15日に最高峰の最南峰の初登頂に成功し、さらにテント・ピーク(5,945m)初登頂というおまけまで得た。さらにいったんカトマンズにもどってから、学生だけが2隊に分かれて、それぞれシェルパ1名を連れただけで、ダウラギリ南面の登路探索とガネッシュ・ヒマール1周の乞食旅行に出発し、十分な成果と満足感をみやげに帰国した。
その後梅棹忠夫先生の指導を得ながら、報告書を出版できた。幸いに評判がよく、書評集まで出すに至った。これについては吉野熙道・上田豊・木村雅昭・島田喜代男 (11) をご覧いただきたい。
以上のような事情から、山岳部の大滝への取り組みは中断されたのだが、その間に以下に述べるような鵬翔山岳会による大滝登攀が成されたのであった。
鵬翔山岳会1962年9-10月 (12) (13) *
再び大滝に戻る。安久一成によると(なお、本記録の転載についての許可を取っていないので、ここには写真と図の転載はしない。末尾の「引用文献・参考文献」で検索してください)、氏が最初に試登を行なった時は大滝尾根を下って最下段の下に達したとのことである。しかしその詳細については、私は知らない。もしかすると、鵬翔山岳会 (12) には記載があるのかもしれないが、この文献は今私の手元にはない。
さらに安久氏 (13) * によると、1962年9月24日から10月3日にかけて、鵬翔山岳会はリーダー:中野満氏以下4名で、十字峡から剱沢を遡行して最下段から10分ほど下にテントを張って登攀にかかった。途中一部分を高捲きしてカットしたものの、大滝の全容を明らかにした。それによると、「大小合わせて九段、落差約百四十メートルであることが判明した。」とのことだった。また彼らは、最下段の滝の高さを京大の実測通り、38mとしている。「たき火のテラス」と呼ぶ台地のふちからF滝(3m)、G滝(7m)を確認した。俯瞰図にはこの下にH滝(20m)、I滝(最下段38m)がある。埋め込みボルトを使用して10m懸垂下降して上流にトラバースすると30mのD滝が見えた。35mで次の中継地、13mさらに10m下り、F滝は3m、目の前に10m のE滝を見ながら登攀、40m斜め左に登り「緑の台地」に着いた。台地左橋のリッジから真上の急なガリーに入って3ピッチで左の岩稜に移る。また2ピッチ登り岩稜を離れ15mトラバースして、計55m空中懸垂下降をまじえてD滝落口に導く尾根に下りて、さらに50mブッシュ帯を下降してD滝落口に立った。上流側に2mのC滝、15mのB滝、7mのA滝を確認した。ここからは小さな尾根にとりつき、B滝の左岸上にのびる急な尾根を登り、下流側に向かい、「トサカ岩」から大滝尾根支稜の下流側を下って、最下段下のベースキャンプを撤収した。A、B、Cの滝の横を上流に上ったわけではないが、彼らの登攀により、大滝の全容は解明されたとしてよいだろう。
くやしかったが、人工登攀を駆使した「石屋さん」に軍配が上がったのであった。
大滝内部偵察1965年8月 (14)
せっかくここまで手掛けた大滝をこのまま終わりにするのはいかにも残念であった。そこで再度の大滝登攀を計画した。しかし事情が許さずに本格的なパーティーを組めなかったので、偵察行という形で、しかし従来とはまったく異なるルートでの大滝接近を試みた。1965年8月21日から8月29日にかけて、吉野と林が再度大滝におもむいた。
23日、仙人小屋から大滝尾根V峰の10分西の岩小屋でビヴァーク。
V峰の50mほど上に右、剱沢に下る小尾根が大滝最上段の滝あたりに下りる、従って滝内部に至るために下るべき尾根と判断した。これは図21中の「桧尾根」と呼んだものである。引き返してまたビヴァーク。
24日、荷物の運び下ろしや北側雲切谷への水汲みなどでしんどい。
25日、雨で沈。
26日、いよいよ大滝に下る。「桧尾根」を下る。垂直の壁に檜やミズナラが真横に突き出しては上に伸びあがっている。鵬翔山岳会が「D滝」と呼んだ30mのナメ滝(吉野が1962年7月に「日電テラス」から撮ったナメ滝)の落口の上、100mくらい上に荷物をデポして、沢身への下りにかかった。デポから水平に10mルンゼをトラバースし、「急な尾根」に取り付き、ブッシュ伝いに約30m下ってブッシュが途切れたので、また約40m左手のブッシュまで岸壁をトラバースしてフィックスを張った。またブッシュ伝いに50mほど下る。ブッシュが切れ、左手70mにブッシュ付きの「小さな尾根」まで外傾気味の岩。そこから林が確保して、吉野が「D滝」の落口に水を汲みに下りた。30分で戻り、18時ころから帰りにかかったが、じき暗くなり、ライトをつけた。とうとうフィックスは見つからずに、ブッシュにぶら下がったビヴァークとなった。
27日、今度は「桧尾根」を下って「A滝」の上に降り立ち、剱沢上流側に少しさかのぼってなんの問題もないことを確認した。水を汲んで、デポに戻った。
28日、何回目ものヤブこぎ、カモシカに会ったり、途中にデポした荷物を回収したりしながら大滝尾根の頭を越えて仙人小屋に帰りついた。翌日馬場島。
これで、鵬翔山岳会が撤収したルートの周辺の状態を知ることができた。雨と水不足、絶え間ないヤブこぎには悩まされたものの、急で次々に枝分かれする尾根や岩を選び下りながら、まちがいなく目指す地点にまで到達することができて、その点では会心の山行であった。
黒部別山より剱沢大滝1968年4月から5月(報告のない個人山行)(15)
吉野はすでに卒業、就職していたが、日ごろ自分が勝手なことばかりして苦労をかけながら、大滝やヒマラヤの自慢話をしてきた同級生に、少しでも悔い改めて感謝していることを示したいものと思っていた。そこで一部スキーを使って、内蔵ノ助平に入り雪洞をベースに、黒部別山より剱沢大滝最下段までをたっぷり1日かけて往復した。運よく最後の滝壺の下に下る所には細々とスノーブリッジがかかり残っていたので、沢身に下りて滝を見ることができた。帰りはみなバテ気味ながら暗い中を雪洞に帰りついて、祝杯をあげた。
大阪市立大学山学部・和田城志、片岡泰彦1976年5月 (16)
1976年5月3日から5月9日まで、 大阪市立大学山学部の和田城志、片岡泰彦の両氏は黒四ダムから十字峡、雪渓通しで大滝に至り剱沢平の岩小屋をベースとして大滝の完全遡行を目指した。
5日から登攀開始。鵬翔山岳会と同様、最下段左岸から「たき火のテラス」、そこから垂直な壁をトラバース、G滝は3mもなく、F滝も5mくらいにしか見えなかったという。鵬翔山岳会の打ったボルト・ハーケンの一部は抜けかけたりして使えなかった。「緑の台地」はデブリの下に埋もれ、E滝は雪渓の下、D滝は流れていた。C滝は雪渓の下に見えた。
8日、「緑の台地」から雪渓上を右岸側に渡り、D滝の右岸を人口登攀で落口まで登り、C滝の右岸をトラバース。A、Bの両滝は雪渓の下で二股手前まで3か所は悪かった。翌日20分で二股、次いで御前小屋に着き、下山にかかった (14) 。図20に彼らのルート図を引用する。
ハーケンは31回使用、ボルトは30本残置したとのことだった。剱沢の雪渓は年によってかなり状態が異なると思われるが、この年は雪渓をフルに使えるよい時期を選んだ登攀であったと思う。
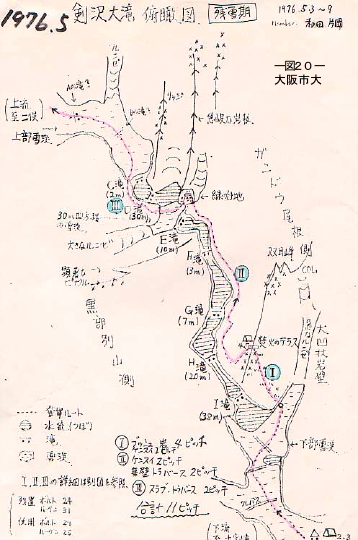
志水哲也1988年 (17)
登山家・山岳写真家の志水氏による単独踏破の記録。つい最近も何回かNHK BSアーカイブスで再放映されている。

謝 辞
下記の文献・資料のうち、京大山岳部報告の全ては上田豊(ポッポ)氏からのコピー提供による。また鵬翔山岳会、大阪市大隊に関する情報も全て、彼がメイルで提供してくれた。彼とはガネッシュ、ヤルン・カンともに苦労をともにした。ここに彼に対して心からの感謝の気持ちを表わしたい。
多くの人たちにとって懐かしい、若かりし昔の記憶をつづった品々はたくさん残っているにちがいない。それらは私のような状態にまで四散、消滅させてはいないであろうが、ほぼ半世紀もの時間が経った今、再び引っ張り出すには多大な労力と時間を要するのだ。これまで私もある程度、心当たりのある人たちに資料提供の依頼を試みたのだが、それに思い至ってあきらめた。
その中で、ポッポはそれこそアッという間にたくさんの資料と情報を送ってくれた。それもあとで聞いたところによると、目にトラブルがあって、資料探しのような作業には大変な苦労がある中でのことだったという。いくら昔のよしみとはいいながら、本当に頭が下がる。改めて、幾重にもありがとうと言いたい。
また以下に、大滝山行に参加したり本文中に登場したりして、その後物故したメンバーの名前を記し、彼らの活躍と山岳部への貢献に対して感謝し、心からの哀悼の意を捧げる。
宮木靖雅は東レに在職中、東海大学よりの委嘱を受け北極圏踏査隊を組織し、1971年隊長として活動中に隊員1名とともに行方不明となった。のちに遺体が発見された。
松田隆雄は1973年、ヤルン・カンの初登頂に成功し、頂上から下山中に転落・行方不明となった。
樋口明生は1983年、病没した。
田村孝夫は1994年、病没した。
岩瀬時郎は2002年、病没した。
引用文献・参考資料
(1) 冠松次郎:「黒部渓谷」、朋文堂新社、東京、1967。
(2) 塚本繁松:「剣の大瀑行」(1932.05.18)、諏訪多栄蔵 辺現代登山全集3「剣 立山 黒部」、東京創元社、東京、1961。
(3) 宮木靖雅:「剣沢大滝」、(京大山岳部報告第9号・1961年12月刊)1960.04.28 – 05.07 (L) 田村孝夫、安原啓示、宮木靖雅
(4)「再び7月大滝を訪ねて」(京大山岳部報告第9号・1961年12月刊)
(5) 宮木靖雅:「剣沢大滝(大滝尾根登攀記録)」(京大山岳部報告第10号・1962年12月刊)1961.07.11 – 07.20 (L) 安田隆彦、富田幸次郎、宮木靖雅、岩瀬時郎
(6) 安岡良祐:「剣沢大滝」(京大山岳部報告第11号・1964年3月刊)1962.07.14 – 07.25 (L) 安原啓示、吉野熙道、安岡良祐、山本武久、野沢正英(読売新聞社写真部員)
(7) 読売新聞:「“幻の滝”を踏破して」、読売新聞1962年9月29日
(8) *朝日写真ニュース:「絶壁にきり込む“幻の滝”」、朝日新聞社、大阪、1962年7月23日。
(9) 京都大学山学部:「インドラサン登頂」、河出書房新社、東京、1964。
(10) 本多勝一:「ニューギニア高地人」、朝日文庫、1981年。
(11) 吉野熙道・上田豊・木村雅昭・島田喜代男:「ガネッシュの蒼い氷」、朝日新聞社、東京、1966。
(12) * 鵬翔山岳会:「幻の大滝を探る」:山と渓谷 286号・1962年12月号
(13) * 安久一成:「剣沢大滝 落差百四十メートルの幻の滝群」(鵬翔山岳会:http://www.geocities.co.jp/Outdoors-Mountain/4753/hsk4m.htm)1962.09.24 – 10.03 (L) 中野満、(アタック)鈴木鉄男、安久一成、(サポート)飯田平八郎、野村彰男
(14) 林国克:「剣沢大滝偵察行」(京大山岳部報告第14号・1967年5月刊)1965.08.21 – 08.29 (L) 吉野熙道、林国克
(15) 吉野熙道:内蔵ノ助平、黒部別山より剱沢大滝往復(報告のない個人山行)1968年4月 - 5月 (L) 吉野熙道、栗田靖之、杉山隆彦、安岡良祐
(16) 片岡泰彦:「剣沢大滝完全遡行」(大阪市立大学山学部:http://www.ocuac.org/domestic/domestic-record/1975turugi/1975turugisawa.htm http://www.ocuac.org/domestic/domestic-record/1975turugi/1975turugisawa.htm) 1976.05.03 – 05.09 (L) 和田城志、片岡泰彦
(17) 志水哲也:「黒部 幻の大滝に挑む」(http://archives.nhk.or.jp/chronicle/B10002200090401030030019/)2004.01.02放映:NHKアーカイブス保存番組*:版権使用許可を取得していないため、写真(別掲)には収録していない。
著者連絡先:
〒701-1211 岡山市北区一宮75-18
E-mail: koppedancingp@msn.com